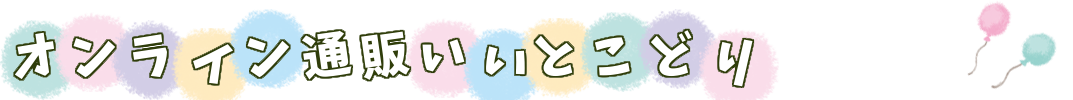広大な土地で悠々と咲く姿に癒される
アジサイを見たくて、6月10日に府中市郷土の森博物館へ行ってきました。JR南武線の分倍河原駅で下車後、1時間に2本の間隔で出ているバスを利用します。覚悟はしていましたが、バスの中は女性ばかりで満席。バスに乗っている全てのグループがおしゃべりをはじめ、バスの案内放送も聞こえません。
停留所の名前が一つもわからないまま着いた終点の府中市郷土の森博物館では、分倍河原駅から乗り込んだ乗客全ての人が降りました。
このバスはJR改札のような仕組みで、乗るときにSuicaを読み取り機械にかざし、降りる時再び機械にかざして乗車区間分の料金が引き落とされます。乗るとき読み込みさせなかった方は、降りる時に運転手に叱られています。暗黙の了解で、Suicaを持っていることが要求されています。初体験なり!!
府中市郷土の森博物館のアジサイのほとんどは、昔ながらの品種です。昨今の品種改良が進んだ華やかなアジサイがなく物足りなさはありましたが、自然の中で悠々と咲いているアジサイの姿には癒されました。

コロナ禍のおすすめの広い公園
とにかく広く、とにかくアジサイの数は物凄いです。アジサイの季節以外には、他の植物も楽しめるようになっているために園内は広大です。博物館やプラネタリウムも園内に隣接していて、大きな大きな公園なのです。
アジサイを見ながら、滝、水車、池、古民家、茶屋、まいまいず井戸なども楽しめました。池は中に入って水遊びができて、多くの子供が遊んでいました。
コロナ禍でも、こうした広い屋外の公園なら1日楽しめそうですね。
咲いていたアジサイをピックアップ
群れを成して半円の花が咲き誇る姿だけでも圧巻ですが、他に私が『おや?』と思ったアジサイの姿をピックアップしてみました。
古民家横のアジサイ
奈良時代から日本で親しまれてきたアジサイは、万葉集にも登場しています。アジサイで有名な寺院もあり、日本古来の風景に似合うようです。古民家をバックにしたアジサイは、ちょっぴりノスタルジックですね。

カシワバアジサイ
このごろよく目にする、三角帽子の形をしたアジサイを見つけました。カシワバアジサイは、咲き始めの緑から白色への変化が楽しめるだけでなく、秋には紅葉もみられます。

アナベルの丘
アナベルは御覧の通り、白いアジサイです。アメリカ産のワイルドホワイトハイドランジアを改良して作られました。6月から7月にかけて緑色の蕾が付いて、花色がしだいに緑色から薄緑色そして白へと変化していきます。
それにしても、この大群は迫力ですね。

近寄ってみると、小さなガクがぎゅっーとひしめき合って咲いています。可愛い💛

今年のタキイ種苗のカタログには矮性のアナベルの苗が掲載されていました。アナベルは今人気ですね。
不思議なアジサイの寄せ植え
郷土の森のアジサイで一番不思議だったのは、下の写真のような光景です。
アジサイって確か、土壌のpHによって花の色が決められるはずなのに、何故、同じ場所でいろいろな色のアジサイが植わっているのでしょう。近くに説明の看板もなく、謎のままです。

しかし、こうした寄せ植えもなかなか素敵です。
下から見上げるアジサイ
低木のアジサイは、いつも上から見下ろすようにして鑑賞しますが、小山の斜面に植えられたアジサイは見上げるように鑑賞しました。なんだか、迫ってくる威圧感がありませんか?

土壌のpHを調節しているのでしょうか?この公園は、青色も赤色も両方楽しめます。

田舎にいる気分になる風景
府中市郷土の森博物館の魅力は、園内の田舎にいるような気分になる風景です。
小川
新宿まで30分前後で行ける場所とは思えないくらい、のどかです。

水車
水車と小屋の周りの生け垣や植物がバランスが良く、違和感を感じません。

滝
下の写真では3本の滝が見えていますが近づいてみると、他にも2本くらいの滝が目に入りました。ちょっとした観光気分になれます。

井戸
ブラタモリでも紹介していた、まいまいずの井戸です。『まいまい』とはカタツムリのことで、らせん状の道を通って井戸端まで行きます。実際に使われていた井戸ではなく、発掘調査の記録をもとに想定復元したものだそうです。

水遊びのできる池
水着を着て小さな子供たちが、水遊びをしていました。塩素のにおいが微かにしましたので、お水は消毒されているようです。

スポンサードリンク