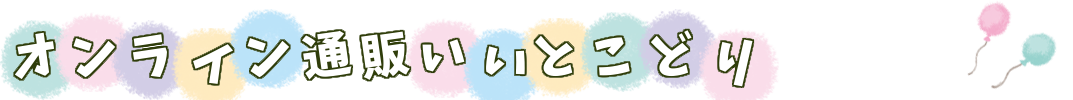雛人形の歴史を紐解けばその姿に納得
雛人形の歴史を知れば、今飾られている人形の姿の意味がわかります。
中国には周公の時代より、旧暦の3月の最初の巳の日に、『上巳の祓(じょうみのはらえ)』という習慣がありました。水辺で身体を清め盃を水に流して、宴が行われていたのです。
これが、平安時代に日本の貴族の伝わり、曲水の宴(きょくすいのうたげ)の始りとなります。水の流れのある庭園で、盃を浮かべて盃が自分の前を通り過ぎる間に、詩歌を読みます。その後、宴でその詩歌を披露し合う行事です。 
最初は教養ある女性が、男性に対する当て擦りだった
この行事には女性は参加することがかなわなかったために、教養のある女性達が、全ての女性が行うことができる流し雛を考案します。最初は、電車の女性専用車両のようなものだったのですね。
最初に使われていた流し雛は、現在のように座っているお雛さまではなく立っていて、紙や藁で作られていました。川に流した立ち雛が、海まで流れきることができれば、雛に身代わりを託した女子が、その年を無病息災で過ごせるという願いが込められていました。
平安時代の女性の願いは、結構悲しいね
当時、平安時代の平均寿命は、男性33歳で女性が27歳ぐらい。乳児死亡率は高く乳児の寿命を除いては、平均で40歳ぐらいと言われています。
特に、女性の方が栄養失調に陥りやすいため、早く亡くなる確率が高かったのです。平安時代の女性の顔は、ふっくらとしたおかめ顔が美人とされていましたが、現実は、栄養失調のむくみが原因でした。
特に、位の高い貴族の女性の場合は、食事をすることがはしたないとされ、少食であったようです。
藁や紙で作られた立ち雛は、男女一対。男性は、女性を守るように手を広げて立っています。男性が女性を守り、女性は男性に従いながら、末永く共に暮していく女性の願いが込められています。
平安時代の貴族は、一夫多妻制でしかも通い婚であったために、女性にとって不利な婚姻関係でした。男女一対の人形は、女性の切実な思いが込められていた感じがしますね。今の人は、なんとなく見ている人形だけど、悲しみが秘められているんですね。
江戸時代に無病息災から玉の輿祈願に加わった
平安時代は、子供の無病息災、幸せな結婚生活といった平凡なことが願いでしたが、江戸時代になると、一気に玉の輿祈願になります。なんだか、人間ってわかりやすいですよね。親としては、裕福な一生涯を送れるることが女性の幸せと考えるのが普通なようで、現代のような華やかな雛人形に、変わっていきました。
豪華な家財道具、三人官女、五人囃子などおつきの人と共に、御殿で暮らせるような生活が、最も幸せの証しとされていたのが伺えます。
現代の雛人形は、身代わり祈願と玉の輿祈願の両方がある
先日から、陶器の雛人形を紹介していますが、立ち雛の時代を連想させる雛人形もありました。素朴で、純粋に子供の幸せを願う親の気持ちが、ひしひしと感じられるはずです。
瀬戸織部焼(おりべやき)
瀬戸織部焼は、桃山時代に岐阜県土岐市付近で始まり元和年間(1615年-1624年)まで、主に美濃地方で生産された陶器です。千利休の弟子 古田織部の指導の元で作られて、奇抜で斬新な形や模様が特徴となっています。
単色使いの人形は、大人になっても飽きずに持ち続けることができそうです。素朴で優雅、ちょっぴり平安時代の悲しい女性の気持ちも伝わってきそうな気がしませんか? 
立ち雛の勇ましい男性の姿と、寄り添うように立っている女性の姿が美しいですね。 
超個性的、超斬新ですねぇ-。 
デカ目のカップルです。女性はつけまつげをしているみたい! 
でか目の雛人形で、白い着物バージョンです。 
何だか超生意気、ちょい悪って感じ。 
みんな同じ背丈、体格なのね。 
もし、孫がいたらコレかな?安そうだし、子供が喜びそうだもの。 
食器棚の隅において、飾れそう。 
豊かでなくても、豪邸でなくても、愛があれば。。。ね。これぞ、現代版雛人形かな? 

薬師窯(やくしがま)雛人形
薬師窯は、愛知県瀬戸市の陶磁工房 中外陶園の窯名です。明治以来瀬戸の地で伝承されてきたセトノベルティの技法により、干支(えと)置物や招き猫、雛人形、五月人形をはじめ、 縁起物や四季折々の季節飾りなどを作り続けてきています。
作りが精巧で、ため息がでました。 
陶器とは思えない質感ですね。 
お揃いの着物だし、お二人とも足が長いですよね。 
こちらもお揃いの着物。 
スポンサードリンク