日本の四季を自宅で楽しめる、ちりめん小物でほのぼの
京都市伏見区にある和雑貨屋さんで、可愛いちりめん小物を見つけました。『京の町家 歳時記』といいます。直径11.7センチ、幅4センチで、手のひらに載せられる大きさです。
本棚の脇や、食器棚の隅、窓枠が幅があれば窓際にちょこんと飾られそうです。
テーマは12カ月の歳時記で12個。まわるい樽をくりぬいて横に置いた中に、昔懐かしい和室の風景と季節の風物詩がチリメンで作られています。しわしわのチリメンの感触と、和風景がピッタリマッチ。
取り上げられている風物詩は誰もが知るありふれたものだけど、何故か心がほっこりするところが気に入りました。 
昔ながらの日本の家と歳時記の風景
各月ごとにテーマが決まっていますが、昔のお宅には見らた円窓やふすまなども一緒に作り込まれていて、芸が細かい!箇条書きにするとこんなところ。
- 1月 御正月・床の間
- 2月 節分・おくどさん
- 3月 ひな祭り・棚袋
- 4月 さくら・座敷
- 5月 子供の日・二階の間
- 6月 梅雨・中庭
- 7月 祈園祭・格子戸
- 8月 大文字・裏庭
- 9月 お月見・円窓
- 10月 柿・隠れ部屋
- 11月 もみじ・野点
- 12月 こたつ・雪見障子
1月 御正月・床の間
年神様をお迎えする御正月は、今年も作物が豊作であるようにとお願いするために、鏡餅が飾られました。 「三方」という、まわるい穴のあいた台の上に鏡餅がのっています。また、細い竹串に10個の干し柿が刺された串柿と、代々家が続きますようにという語呂合わせから橙が鏡餅の上にあります。
右横には階段タンス。今は骨董屋で購入しようとすると、目から火が出るほど高い階段タンスですが、昔は普通のお宅にあったのですね。
床の間である事がわかるように、後ろには掛け軸が飾られています。
2月 節分・おくどさん
京都などでは竈(かまど)を意味する、『おくどさん』が置かれて、台所の風景のようです。電子炊飯器が無かった時代は、かまどに火を炊いて鉄鍋でお米を炊いていました。決して大昔ではなく、70年くらい前までは、あった風景なのです。
2月と言えば、節分。豆まきをして、鬼を退治して福を家に呼び込む行事があります。福の神のお面と散らばった大豆があるので、豆まきが終えたばかりなのでしょうか?
節分に食べると縁起が良いと言われている恵方巻き(太い巻き寿司)も、まわるいちゃぶ台の上に置かれています。ちゃぶ台の後ろには棚が置かれていて、味噌壺やすり鉢とすりこぎなども並んでいます。
3月 ひな祭り・棚袋
床の間の脇に作られる、ふすまをつけた小さな戸棚は、上につけたら天袋、足元につけたら棚袋と呼ばれるようです。中央には、高い違いの棚があって、茶器や壺などが飾られていたのです。
当商品『京の町家』では、棚袋の上にお雛様がのっています。お内裏様とお雛様、3人官女、ぼんぼりや菱餅などもあります。
菱餅は、健やかに子どもが成長できると言う願いを込められているそうです。
4月 さくら・座敷
障子があるお宅も減りました。半分開けられた障子の外に、縁側があり3色の団子が添えられています。
桜の木があるお宅なのでしょうか?白とピンクの桜の花びらが、部屋の畳の上にも落ちています。
石灯籠や苔の生えた小山も庭に作られているようで、かつての武家はこんな風にお花見をしたのかと、想像させられます。
5月 子供の日・二階の間
立身出世を願う男子の節句、子供の日の月です。2階の窓から、黒と真っ赤な鯉のぼりが見えます。
ちまきや柏餅を食べ、菖蒲湯に入ってお祝いする風習は、現在も行われています。
6月 梅雨・中庭
カタツムリを見ることが少なくなりました。6月の風物詩、アジサイ、カタツムリ、てるてるぼうずが飾られています。番傘やすだれがなんとも、京都チックです。
この時期は、旧暦で五月雨(さみだれ)と呼び、雨の降る夜の事を五月闇、梅雨の晴れ間の事を五月晴れと言うのだそうです。
7月 祈園祭・格子戸
7月に京都で行われる祈園祭は、日本三大祭りのひとつ。17日と24日に行われる33基の山鉾巡行「京都衹園祭の山鉾行事」はユネスコ無形文化遺産になっています。
提灯をつけて巡行する鉾の後ろでは、スイカが切られていて美味しそう。
8月 大文字・裏庭
京都の夏の夜空を飾る「五山おの送り火」は、東山如意ヶ嶽の「大文字」が有名です。他、松ヶ崎西山・東山の「妙・法」、西賀茂船山の「船形」、金閣寺付近大北山(大文字山)の「左大文字」、嵯峨仙翁寺山(万灯籠山・曼荼羅山)の「鳥居形」となります。
豚の蚊取り線香、風鈴、うちわと、懐かしいものばかり。
9月 お月見・円窓
「三方」の上に、満月のようにまん丸の月見団子が、三角形に飾られています。ススキ、隣には何故か白い兎がいます。円窓の向こう側には、大きな大きなお月さまが、それはもう大きく輝いています。旧暦8月15日を、十五夜、中秋の名月と呼ぶのはご存知のとおり。
10月 柿・隠れ部屋
実りの多い秋は、果物も豊富となります。かつての民家の庭には、柿やビワなどを作っているお宅もありました。
トンボや猫が縁側に訪れて、もう日本人ならでは誰でも郷愁を誘われます。
11月 もみじ・野点
京都では、「抹茶たて体験」できる場所があるそうです。
真っ赤な野点傘の下に、毛せんがかけられた床几(しょうぎ)があります。時代劇で、お侍さんが外でお茶を飲む時、こんな風景があったかも。お馴染みの抹茶茶わん、風炉釜、柄杓なども一緒です。
京都の紅葉を見ながら、抹茶をたしなむなんて風流ですよね。
12月 こたつ・雪見障子
雪景色が見える襖の日本間には、昔ながらの炬燵があります。定番のみかんと、ネコもちゃんといるんです。
こちらのちりめん細工は、月毎に個別に購入することができます。
|
|
スポンサードリンク
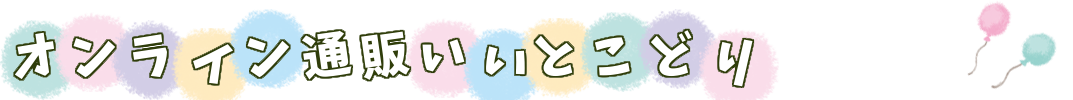
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14c14c45.5e4c8979.14c14c46.697f07cb/?me_id=1204896&item_id=10004862&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyumemiya%2Fcabinet%2F05308622%2Fimgrc0065127580.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyumemiya%2Fcabinet%2F05308622%2Fimgrc0065127580.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

