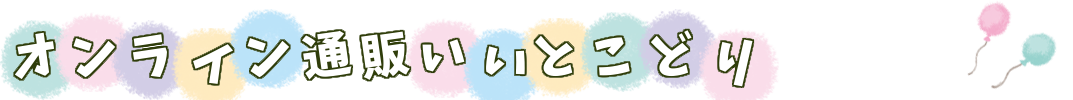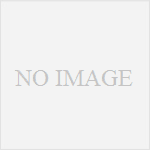バラのプリザーブド、やっぱり人気は赤みたい
バラのプリザーブドフラワーを、飾ったツリーやリースをよく見るようになりました。当ブログで何度か紹介してきた、ツリーやリースにもバラはが使われていました。
でも、『何でバラなんだろう?』、『いつからバラになったんだろう?』って思いませんか?
私が子供の頃はバラの花を飾っていなかった
子供の頃のツリーに飾るオーナメントは、こんなところ。ちょっと調べてみましたら、それぞれにキチンと意味があったのですね。
- ツリーのてっぺんに、大きな金色の星東方の博士(賢者)たちを幼子イエスへと導いた星
- キャンドル「世を照らす光」としてキリストを象徴している
- ベル救世主であるキリストの誕生を知らせる喜びのベル
- 赤と白のしましまの杖キリストの誕生を世間に知らせたのは、羊飼いの方達で、羊飼いが持っていた杖を表す赤には、十字架でキリストが流した血、白には、キリストの清い心
- 靴下サンタクロースがプレゼントを入れるように
- まんまるい赤い玉りんごを意味していて、禁断の実とか神の恵みのいわれから
- ひいらぎ十字架にかけられるキリストが、頭に被せられたイバラの冠の象徴
- 十字架キリスト教と言えば、十字架ですよね。
私が子供のころには、バラの花を飾る習慣はありませんでした。でもクリスマスツリーの元祖を調べてみると、ありました!
クリスマスツリーを飾る習慣は、ゲルマン人が暮らすライン川の東部から始まっています。古代ゲルマン人は、長くて暗い冬を愉快に過ごすために、小さな動物の木彫り等を作って、近くのモミの木に吊るして暮らしていました。
その後、ドイツにキリスト教が布教されて、もみの木のてっぺんに星を飾り、キリストの誕生を祝うツリーに変わっていったのです。
1605年には、すでにストラスブールの市民が家の居間にモミの木を置き、色紙で作ったバラの花、リンゴ、ウェハース、金箔、お菓子などで飾りつけていたそうです。 
住宅街から人気のリースを探る
今年、住宅街の中を歩いていると、華やかなリースを飾った家の一団をみました。
クリスマスにリースを飾るのは、少なくとも私の子供のころにはなかった風習で、やはり年配者が多い町内会では、そう見られません。私の近所も残念ながら、飾っているお宅はそう多くはありません。
新興住宅街か、お子さんがいるお宅で良く見ます。1件のお宅が飾り始めると、”あ~なるほど”って思うのでしょうか、周辺のお宅も飾っていくようです。
よく目に入ったのは、姫リンゴや赤い実のリースです。赤いバラのリースも見ました。
りんごは、旧約聖書に出てくるアダムとイブの禁断の実です。神に食べてはいけないと忠告されたのに、蛇に騙されて、食べちゃったんですよね。
中世ドイツの教会で、クリスマスイブの日に、この『アダムとイブ』の劇が演じられた時に、りんご木が置かれていたということです。それ以来、ツリーにりんごが飾られるようになったそうです。
プリザーブド技術でバラを飾ることが可能に
もともと赤いバラはキリストの血で、白いバラは聖母マリアの象徴とされています。バラは神にささげる薬草として使われて、修道院などで栽培されていました。そのために、一般の人はバラを栽培することができなかったのですよ。
キリストの生誕を祝うリースやツリーに、バラの花を飾るのは、ごく自然なことだったのですね。でもきっと、オーナメントとして作るのに、コスパ―が悪かったに違いないって勝手に思うのです。
生花をドライフラワーとして長く楽しむ方法を知り、さらに、プリザーブドにすることで、何年も楽しむこと技術ができたから、こうしてリースやツリーに飾って、楽しむことができたのだと思います。
プリザーブドは、湿度に弱いので、梅雨時には外気に触れないようにして保管すれば、2~3年は持つと言われています。
当サイトでもクリスマス用の花は、日比谷花壇とイイハナのものを紹介しています。
スポンサードリンク