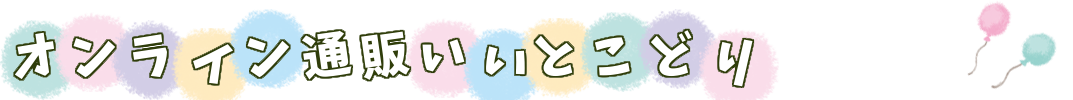種の存続の仕組みに感心
稲垣栄洋氏が書いた『生き物の死にざま はかない命の物語』を、読みました。様々な生物の死の瞬間に視点をおいて書かれています。
この本で、動物も虫も常に死と隣り合わせ、でも種が絶えないのように生態系で絶妙な仕組みをもっていることを知ります。生物も絶滅しないで生き続けてきた理由の中には、一度に出産する子供の数が多かったり、信じられない子育てにあるようです。
地球上に初めて現れた生物が何億年もかけて進化し続けるうちに、個々の生物が各々独自に子孫を残すための仕組みを作り上げてきたに違いありません。感心してしまうばかりですね。

命を張って子育て
子供を育てられるということは、強い生物に与えられた特権だと筆者は言います。哺乳類や鳥類が子供を育てられるのは、子供を守ることができる強さを持っていることです。弱い生物の場合、それができないために、卵を産みっぱなしにせざるを得ません。
ところがどうでしょう。弱いと思われている虫達も、子育てをしているのです。
中でも強力な毒を持つカバキコチグモは、わが子に自分の体を差し出し体液を吸わせて子育てをします。母親が弱って体力がないからなのかと思いきや、敵が現れると攻撃を仕掛けてくるそうです(赤ちゃんを守るために)。
皇帝ペンギンのオスは厳しい冬の寒さの中で、足の上に卵を載せて食事もしないまま温め続けると言います。もし、餌を探しに行っているメスが戻ってこなければ、オスには飢え死にしてしまうペンギンもいます。
子供の死亡率が高いと次々と子供を産む
百獣の王と言われているライオンの生後1年以内の死亡率は、意外にも60%を超えるのだそうです。

その死因は『飢え』です。草食動物を食べるための狩りの成功率は、人が思うほど高くありません。たとえ獲物を捕らえたとしても、群れの中で食事をする順序は、ボスであるオスが1番、次に母親、最後に生後間もない子供と続きます。そのため、飢え死にしてしまいます。
そのためライオンは、一度の出産で二、三頭の子供を産み保険をかけているのですね。
一方、ライオンの餌となるシマウマやヌーなどの草食動物は、一度の出産でたった一頭の子供を産むだけです。ライオンと比べて生存率が高いことが想像できます。なんといっても、餌はどこにでも生えている草ですからね。
世界最速の哺乳類といわれているチーターは、生まれつきのハンターではありません。狩りの方法を母親から教わりますが、やはり難しいのでしょう。無事に大人になることができるチーターは、10~20頭に1頭です。チーターもライオンのように、一度に子供を一から八頭も出産します。
寿命が短いと出産の数が多い
ゴキブリは3億年以上も前から存在した、『生きた化石』です。恐竜さえも生き延びれなかった時代を易々と、乗り越えてきた最強の虫です。
しかし、ゴキブリの寿命は半年から1年ほどで短命。この短い間に何度も卵を産み、子孫を残すのです。そういえば、ゴキブリをたたき殺すと卵を産むと聞いたことがありますが、ほとんど常に卵を抱えている可能性があるということなのですね。
群れを成して移動し外敵のターゲットを絞らせない
魚編に弱いと書くと、イワシ(鰯)です。多くの魚の餌となるイワシは、大群で移動しています。
こうして群れることで、敵からの攻撃を防げるわけではないけれど、自分が食べられる確率が低くなります。的を絞らせないことで、一匹、一匹が襲われにくくなるのだそうです。
『生き物の死にざま はかない命の物語』のアマゾンのURLはこちら。
スポンサードリンク