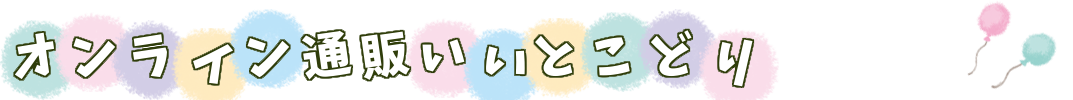自然の息遣いを知って暮らしたくなった
四季の移り変わりは、植物、動物、虫、気候の変化で実感するものです。春夏秋冬が順に訪れると1年が終わり。再び迎えた春に同じ風景が巡ってきます。自然を受け入れ、季節の自然がもたらす恵みを喜んだり、試練に耐えて対策を練ったりして暮らしているのです。
時には自然の不思議な光景に驚いたり、見慣れた雑草や虫で季節を知らされたり、寒さや暑さをしのぐ工夫を楽しんでみたりしながら、積極的に自然と向き合うこともあります。農業とか漁業といった自然を相手に仕事をする方なら、尚のこと、自然は全てで頭から離れることはないでしょう。

当たり前の自然との共存ですが、それほど気にかけないで暮らすことも可能です。学業や仕事に専念することだけを、大切にして四季なんてどこ吹く風といった具合です。多くの人はどちらかというと、こうしたタイプに違いありません。
話はそれますが、かつて地方のホテルに缶詰めになって仕事をしていた同僚が、「半袖だったのが、気が付いたらコートが必要な季節になっていた」とぼやいていましたが、これが多くの人の現状に違いありません。
人の暮らしにも四季がある
ところがですよ。学業にも仕事にも節目があり、人の営みの節目と、季節は密接な関係はあります。やっぱり人間の暮らしも四季があるのです。新学年、新社会人の姿は、新芽がまぶしい野鳥のさえずりをよく耳にする春です。”新しい”と”春”はとっても良く似合いますね。
人の暮らしも、四季に似ています。
俳句は暮らしと季節を結びつける道具
俳句は、必ず季語を添えて語らなければならないので、おのず暮らしと季節を重ねて考えてしまいます。俳句を作るためには、四季の移り変わりに鈍感ではいられません。
川上弘美さんの『わたしの好きな季語』を読んで、植物、動物、虫、気候の変化を、もっと知りたい、もっと実感しながら暮らしてみたいと思うようになりました。自然の息遣いを知ることは、生活に彩を与えてくれます。

小説を引き立て、読者をのめり込ませているのは、小説の中の自然描写が素晴らしいからと川上さんはいっています。細部までこだわった舞台装置のもとで行われる演劇と、殺風景な舞台で行われる演劇とでは訴える強さも違ってくるのと同じことかもしれません。
人がその時々を輝いて生き生きさせているのは、実は周りを取り囲む自然の力も関係しています。
『わたしの好きな季語』には、一つの季語をさらに細かく表現した季語を紹介していました。季節を虫眼鏡で眺めて、それでも我慢できずに顕微鏡まで持ち出して観察しているように思えます。
時雨
時雨【しぐれ】は、冬の間の寒い時期に降ってはやみ、やんでは降るものさびしい雨を指します。しぐれという音の響きも美しいし漢字も美しいと、川上さんは書いています。
まさしく。ですね。
時雨には、朝降る「朝時雨」、夕方は「夕時雨」、夜は「小夜時雨」と、時間によって言い分けられます。さらに、少し強めの時雨が通り過ぎるさまを「村時雨」、あるところには降っているけれど、あるところには晴れている様子を「片時雨」というのだそうです。
これは面白いとネットでも調べてみたら、出てくる出てくる、これほど美しい言葉を使わずにはいられないと気持ちが伝わってきます。地方ごとに、北山時雨、高島時雨、七時雨山と命名されています。冬だけの季語にさせておくのはもったいないと、「春時雨」、「蝉時雨」があり、ことに冬のその年に降った最初の時雨を「初時雨」というのだそうです。
十五夜(中秋の名月)
名月もよく俳句で使われる季語ですが、十五夜は年に1回、旧暦8月15日の夜のことを指すそうです。他の月には、満月になることを表す言葉はありません。十五夜への強い思い入れが、こんなことからも伝わります。
十五夜当日に見える月が、明るく満月に見えれば「名月」、雲に隠れて見えなければ「無月」、雨が降って見えなければ「雨月」となります。
十五夜の前の夜は「待宵」、翌日は「十六夜」、さらに翌日は「立待月」、さらに翌日は「居待月」、さらに翌日は「臥待月」さらに翌日は「更待月」、そして「更待月」以降の月は10時過ぎにならないと登らないために、月が出るまでの闇を「宵闇」というのだそうです。
十六夜、十七夜、十八夜・・・としないて、1日1日名前を付けていった人々の、十五夜にかける特別な強い思いがヒシヒシと伝わってきませんか?
『わたしの好きな季語』をアマゾンでチェックするならこちら。スポンサードリンク